代表 井澤 紳太郎
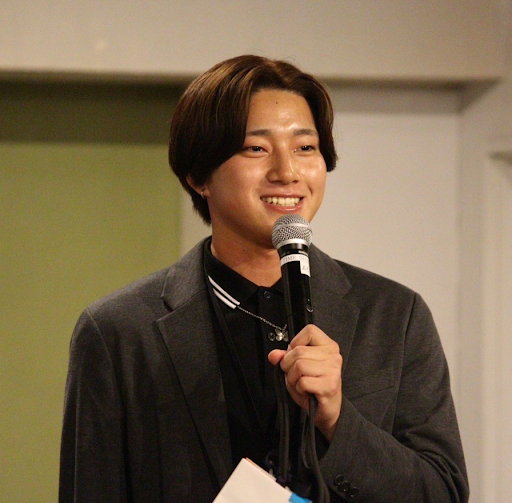
これからの教育は非認知能力にフォーカスすること
大手中学受験・高校受験対策塾に2年、大学受験対策塾に4年間従事。
大学受験対策塾では本部校の校舎運営を務め、たくさんの受験生を指導してきた。教育業界での指導経験を重ね、自身の学生時代を振り返る中で非認知能力(non-cognitive skills)の重要性に気づく。受験で求められる学力(認知能力-cognitive skills)の向上に繋げるためにはもちろんのこと、大学卒業後の社会人としての長い人生に求められる力を伸ばすためには非認知能力の存在に気づき、身につけていくことが重要であるという教育理念を持つ。
より多くの人に非認知能力の重要性を知って欲しいという想いから「ノンコグナビ」を立ち上げ、教育の新たなあるべき姿の実現を目指している。
校舎長 やまざき

非認知能力の種を蒔く
大学受験対策塾にて3年間生徒指導に従事。
自身の中学受験を経て、「自調自考」を教育理念とする私立の中高一貫校に進学。中学1年生の頃から校長先生の講話で繰り返し「非認知能力の大切さ」が語られていたものの、当時はその意味を十分に理解できていなかった。
しかし大学生になり、多方面で活躍している中高時代の同級生たちを見てあることに気付く。彼らに共通していたのは、学力以上に「物事に主体的に取り組む力」や「人と信頼関係を築く力」といった非認知能力だった。今になってようやく、あの頃の校長先生の言葉が、自分の中に“種”として蒔かれていたのだと実感している。
私自身、非認知能力をまだまだ伸ばしている最中だが、「社会を生き抜く力」は「学力」だけでは培えないことを実感している。だからこそ、生徒のみなさんに小さな“種”を蒔くお手伝いをしたい。
副校舎長 ひらの

「学習塾に通わなかったこと」が大学受験の成功に繋がった
学習塾に通わずに大学受験の勉強を進め、第1志望校に合格。この経験を活かし、大学受験対策の指導に4年間従事。
講師として受験指導に携わる中で、「同じ指導内容・宿題を与えても、成果に大きな個人差が出る」という課題に直面。その主因は「自ら頭を使って考え、志望校合格=目的達成のために主体的に行動できているかどうか」だと考えた。受験生時代、独学だったからこそ、日々「今、自分は何をすべきか」を自問しながら学習を進めることを心がけていた。その積み重ねが自ら考えて行動する習慣につながり、結果的に大学受験の成功に結び付いたのだと講師になって初めて実感。一般的な学習塾では、講師やチューターの細かな指示がかえって生徒が“自分で考える力”を発揮しづらくしている。
ノンコグナビで、一般的な学習塾では育てにくい非認知能力を伸ばすお手伝いをしたい。
講師 おおもと
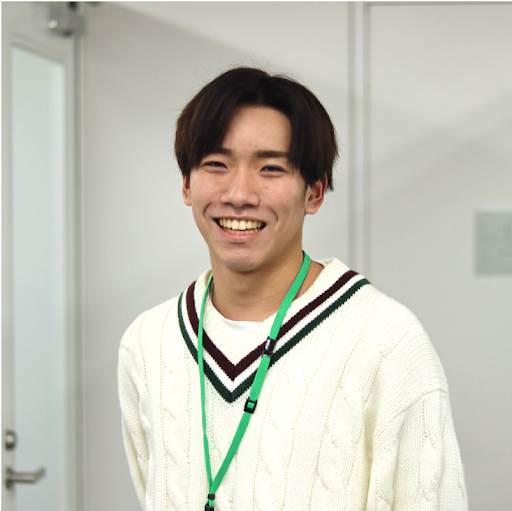
非認知能力こそ、最大の受験対策
大学受験対策塾にて3年間生徒指導に従事。
部活動やインターンなどの経験を通じて、自分から意見を発信する「主体性」の大切さを実感。特に、周囲がためらうような場面でも一歩踏みして行動することで、環境やチームを少しずつ前向きに変えていく力を持てた。
大学受験の塾で3年間講師を続ける中で、成績を大きく伸ばす生徒には「非認知能力」が共通して高いことに気づいた。継続する力、自分で逆算的に計画を立てる姿勢、そして最後までやり切る意志の強さが重要であり、塾そのものに投資するよりも、非認知能力を育てることこそが、最も価値のある教育だと考えている。
この場を通じて、生徒たちの「見えない力」を一緒に育てていきたい。
講師 ねもと

「勉強の意味」
大学受験対策塾にて2年間生徒指導に従事。
受験勉強を進めていく中で、「勉強の意味」を考え始める。「why思考」「タスクの優先順位」「信頼している人への相談」を取り入れることで勉強を効率的に進め、第一志望校に合格。
大学生になり、大学受験対策塾で生徒指導をしているうちに、成長する子には「why思考」「主体性」「客観性」といった共通点があった。ここで「勉強の意味」とは「非認知能力」を高めるという「社会で生きていく力」を育成するものであると考えた。大学受験時に無意識にした行動は全て「非認知能力」によるものであり、生徒指導をしていく中で「非認知能力」を高めることの重要性に気づかされた。生徒の「非認知能力」を集中的に伸ばし、無限の可能性を広げていきたい。
